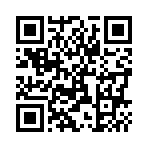2016年09月10日
新潟県警・陸上自衛隊 柏崎刈羽原発において対テロ合同訓練

平成27年10月29日、新潟県柏崎市と刈羽郡刈羽村に所在する東京電力柏崎刈羽原子力発電所において、新潟県警察と陸上自衛隊による初めての合同対テロ訓練が実施されました。
訓練では、原発周辺に重武装の武装工作員(ゲリラ・コマンドウ)が上陸したとの情報を得て、警察力のみでの対応が困難と判断した総理大臣が自衛隊法に基づく治安出動を発令した状況を想定。
県警機動隊所属の銃器対策部隊の隊員約60名と上越市高田駐屯地に所在する第12旅団第2普通科連隊所属の隊員約70名が訓練に参加しました。
我が国に武装工作員が上陸し、自衛隊が治安出動して対処するという想定は、十数年前に公開された「宣戦布告」という映画(原作は小説)を想起させます。
 |
この作品では福井県敦賀半島に北朝鮮の潜水艦が座礁し、自動小銃やRPGなどで完全武装の工作員11名が上陸したという設定で、警察力での対処が困難と判断した政府により、自衛隊法に基づく治安出動命令を受けた自衛隊が掃討作戦を実施します。しかし、法律上の武器使用の問題点や政府関係者の弱腰な姿勢などから現場では多数の犠牲者が生まれ、有事における現行法の脆弱性を問題提起したことで大きな反響を呼びました。
なお、この作品自体も1996年に実際に発生した北朝鮮による韓国への潜水艦侵入事件「江陵(カンヌン)浸透事件」をモデルとしており、その設定は決して荒唐無稽なものではなく、工作員の上陸を許していた我が国においても現実に十分起こり得る事態といえます。
さて、せっかくなので自衛隊の治安出動について、おさらいしたいと思います。少し長くなるので、興味のない方はスルーして下さい。
この治安出動の根拠法令は、防衛出動などを定めた自衛隊法第六章「自衛隊の行動」の条文であり、
(命令による治安出動)
第七八条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
とされています。
防衛出動が我が国に対する明白な侵略行為への対処のため、自衛権に基づく自衛隊の幅広い「武力行使」を認めたものであるのに対し(国際的に見れば事実上の戦争ないし紛争状態)、国内の治安維持を目的とした治安出動では自衛官による必要な「武器の使用」が認められているだけです。
元来、治安出動は1960年代に活発化した安保闘争運動や極左暴力集団による破壊活動の深刻化を受け、警察力では対処できない規模にまで拡大した暴動や騒擾への自衛隊出動を想定していましたが、現在では今回の訓練想定のように武装工作員(ゲリラ・コマンドウ)によるテロやゲリラ活動への対処も大きな目的となっています。
そして治安出動を命ぜられた自衛官については、自衛隊法第七章「自衛隊の権限」において
(治安出動時の権限)
第八九条 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の規定は、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第四条第二項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。
と規定され、警察官の職務権限等について定めた警察官職務執行法(警職法)上の条項全てが自衛官に準用されます。
つまり、武器の使用についても警職法第7条(武器の使用)の規定が準用され、
・凶悪犯人の逮捕又は逃走の防止
・公務執行に対する抵抗の抑止
・正当防衛若しくは緊急避難
のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、初めて武器の使用が許されるのです。
なお、自衛隊法の規定により、この武器の使用については、正当防衛若しくは緊急避難を除いては、部隊指揮官の命令によらなければ実行することができません。
また、治安出動時の自衛官の権限について、警職法上の武器の使用についての条項のみに注目されがちですが、法規上は警職法の全ての条項が準用されると規定しているわけですから、
・職務質問
・要救護者の保護
・避難等の措置
・犯罪予防のための警告・制止
・職務執行のための立入
についても自衛官にその権限が与えられ、刑事訴訟法上の司法警察職員がもつ司法警察権などを除き、治安出動中の自衛官は警察官に準じた行動ができることになります。
裏を返せば、警察力で対処できない事態への治安出動を命じられても、その武器使用については厳格な「警察比例の原則」に従う必要があります。
俗に治安出動命令を受けた自衛官を「軍服を着た警察官」と比喩するのはこのためです。
冒頭で紹介した「宣戦布告」において、問題となっていたのは正に警職法に準じた武器使用の規定でした。
ざっくりと自衛隊の治安出動の概要について述べましたが、防衛出動と同じく自衛隊発足から今日に至るまで自衛隊に治安出動が発令されたことは一度もありません。
それは、治安出動による自衛隊の行動が諸外国から見れば軍事力を国内の治安維持に投入するのと同義であり、国家が自国の非常事態を認めたことになるからです。
自衛隊の治安出動は、警察力の限界を超えた国内治安維持の最後の砦なのです。
今回の想定のような現実の自衛隊の治安出動に際しては、公共の秩序の維持という共同目的を達成するため、情報交換や脅威への共同対処をはじめとして、警察や関係機関との協力体制が必要不可欠です。
単純な武力では自衛隊が圧倒しますが、平素から原発の警戒警備にあたる原子力関連施設警戒隊を構成する銃器対策部隊は、原発警備の訓練や教養を受けたプロフェッショナルといえ、原発警備については門外漢の自衛隊が学ぶことも多いはずであり、その逆も然りです。
2011年に発生した福島第一原発事故は、原発の構造的脆弱性を世界に露呈すると同時に、冷却用の電源装置さえ破壊すれば、少数精鋭の工作員だけでも原子炉をメルトダウンさせ、国家を混乱に陥れることが可能なことを世界中のテロリストに証明してしまいました。
特に日本海側に面して長大な海岸線を有し、世界最大規模の原発を擁する我が県では、このような訓練を今後も積み重ね、世界的な課題となっている原発テロへの脅威など、来るべき有事に備える必要があります。
昨年のニュースになりますが、今後も過去全国で行われた同種の公開訓練については、自身の備忘録と資料化を兼ねて随時ご紹介したいと思います。

▲県機動隊所属の銃器対策部隊からは約60名の隊員が参加。平素から原発の警戒警備にあたる原子力関連施設警戒隊も同隊の隊員から選抜されている。
出動服の上から全国の銃器対策部隊でも導入されている防弾前垂れと防弾腕帯付きの突入型防弾衣を着用、頭部の防弾帽は防弾面付きのジェットタイプだ。
特殊銃と呼称されるH&K社製MP5Fには、Aimpoint社製COMP M2ダットサイトとB&T社製TL-99タクティカルライト付きハンドガードが装着されている。
他の都道府県警察では、さらに腰周りに貸与品の帯革を着用して警棒や手錠、拳銃を携帯することが珍しくないが、今回の参加部隊は帯革を着用していない。
出動服の上から全国の銃器対策部隊でも導入されている防弾前垂れと防弾腕帯付きの突入型防弾衣を着用、頭部の防弾帽は防弾面付きのジェットタイプだ。
特殊銃と呼称されるH&K社製MP5Fには、Aimpoint社製COMP M2ダットサイトとB&T社製TL-99タクティカルライト付きハンドガードが装着されている。
他の都道府県警察では、さらに腰周りに貸与品の帯革を着用して警棒や手錠、拳銃を携帯することが珍しくないが、今回の参加部隊は帯革を着用していない。

▲上越市の高田駐屯地に所在する東部方面隊隷下第12旅団第2普通科連隊から約70名の隊員が参加。柏崎刈羽原発は同隊の防衛警備担当地域である。
殆どの隊員が防弾チョッキ2型改を着用しているが、一部の隊員は2014年ころから配備が始まったばかりの最新装備である防弾チョッキ3型を着用している。
88式鉄帽に加え、市街地戦闘を想定してニーパッドとエルボーパッドを装着。主武装は89式5.56mm小銃だが、一部士官のみ9mm拳銃を携行していた。
殆どの隊員が防弾チョッキ2型改を着用しているが、一部の隊員は2014年ころから配備が始まったばかりの最新装備である防弾チョッキ3型を着用している。
88式鉄帽に加え、市街地戦闘を想定してニーパッドとエルボーパッドを装着。主武装は89式5.56mm小銃だが、一部士官のみ9mm拳銃を携行していた。

▲整列した自衛隊員と銃器対策部隊員。治安出動を命じられた自衛官には警察官職務執行法が準用されるが、警察官のように刑事訴訟法上の司法警察権
を行使することはできない。従って、私人でも可能な現行犯逮捕を除き、被疑者(暴徒やテロリスト)の逮捕拘束に関する擬律判断は、警察官(司法警察職員)
である銃器対策部隊員が行う必要がある。警察と自衛隊の相互運用上の理解を深めるこのような共同対処訓練は、現実の治安出動に際して必要不可欠だ。
を行使することはできない。従って、私人でも可能な現行犯逮捕を除き、被疑者(暴徒やテロリスト)の逮捕拘束に関する擬律判断は、警察官(司法警察職員)
である銃器対策部隊員が行う必要がある。警察と自衛隊の相互運用上の理解を深めるこのような共同対処訓練は、現実の治安出動に際して必要不可欠だ。

▲陸上自衛隊で唯一、空中機動力を高めた即応近代化旅団である第12旅団は、ヘリコプターを駆使したヘリボーン戦術による緊急展開能力を重視している。
今回の訓練では、北宇都宮駐屯地に所在する第12ヘリコプター隊第1飛行隊所属のUH-60JAブラックホークが銃器対策部隊の人員輸送を実施した。
今回の訓練では、北宇都宮駐屯地に所在する第12ヘリコプター隊第1飛行隊所属のUH-60JAブラックホークが銃器対策部隊の人員輸送を実施した。

▲降着したUH-60JAから完全武装した銃器対策部隊の隊員8名が一斉に飛び降りる。迷彩塗装の自衛隊機から、機動隊員が現れるのは異色の光景だ。
1機40億円近い高額から陸上自衛隊における保有数も40機に満たないUH-60JAを使用して訓練ができるのは、県警にとっても貴重な機会だろう。
1機40億円近い高額から陸上自衛隊における保有数も40機に満たないUH-60JAを使用して訓練ができるのは、県警にとっても貴重な機会だろう。

▲ヘリを離れた8名の隊員は隊列を組み、全方位を警戒しながら駆け足で車両待機位置まで移動する。

▲伸縮式銃床が伸ばされたMP5は、射撃待機姿勢のロー・レディーないしハイ・レディーの位置で構えられ、脅威があれば直ちに制圧射撃が可能な状態だ。

▲防弾帽の防弾面は跳ね上げられているが、これはMP5の銃床を使用した頬付け姿勢での精密射撃を直ちに行えるよう想定したためと思われる。

▲防弾前垂れや防弾腕帯の標準装備された近接戦闘向け突入型防弾衣の導入により、各都道府県警察が保有する銃器対策部隊の印象は大きく変わった。
近接戦闘に必須であるダットサイトやタクティカルライトを装着したMP5の運用もあって、装備だけを見れば諸外国の警察特殊部隊と大きな差異はない。
近接戦闘に必須であるダットサイトやタクティカルライトを装着したMP5の運用もあって、装備だけを見れば諸外国の警察特殊部隊と大きな差異はない。

▲側道に待機中の機動隊の大型人員輸送車に足早に乗車する隊員。乗車口付近では、部隊の乗車完了まで2名の隊員がMP5を構えて周囲を警戒する。

▲完全武装の銃器対策部隊員を乗せた人員輸送車は、原発施設に向けて直ちに発進する。

▲自衛隊機による人員輸送訓練の詳細想定は報道されていないが、実際の治安出動では原発に常駐している原子力関連施設警戒隊の増援部隊として、
新潟市から銃器対策部隊を自衛隊機で輸送する想定が考えられる。当然、県警もヘリを運用しているが、完全武装の隊員を複数輸送可能な中型機は2機
のみで、定期整備による運航停止や人命救助任務による出動を考慮すると常に県警のヘリが使用できるとは限らず、自衛隊機という選択肢も必要となる。
新潟市から銃器対策部隊を自衛隊機で輸送する想定が考えられる。当然、県警もヘリを運用しているが、完全武装の隊員を複数輸送可能な中型機は2機
のみで、定期整備による運航停止や人命救助任務による出動を考慮すると常に県警のヘリが使用できるとは限らず、自衛隊機という選択肢も必要となる。

▲県警のパトカーが自衛隊車両を先導する訓練も実施された。道路交通法施行令により、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車は
緊急自動車とみなされ、緊急自動車指定を受けていない自衛隊車両でも緊急走行が行えるため、治安出動においても迅速な現場臨場が可能となる。
緊急自動車とみなされ、緊急自動車指定を受けていない自衛隊車両でも緊急走行が行えるため、治安出動においても迅速な現場臨場が可能となる。

▲装甲車両として、第2普通科連隊所属の軽装甲機動車及び82式指揮通信車が参加した。

▲自衛隊車列の後続は偵察オートバイが並び、車列の殿を緊急走行が可能な機動隊の特型警備車が務めることで、緊急走行の完結性を保っている。
日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)公式サイト
 |
2016年07月24日
最近の陸上自衛隊普通科隊員装備 #02

先日の護衛艦「せとぎり」一般公開イベントにおいて装備展示を行っていた陸上自衛隊第12旅団第30普通科連隊の皆様に引き続きフォーカスをあてていきます。
なお、前回の記事はこちらを参照願います。

▲ムック・・・ではなく、全国の普通科連隊に創設されている狙撃班の隊員がギリースーツを着用し、会場内を歩いていた。ギリースーツに対する一般人の馴染みは薄く、その近寄りがたい存在感から興味があっても遠巻きに眺める人が多い。

▲防弾チョッキなど装身具の展示コーナーを担当していた方の装備。2014年ころから配備が始まった最新装備である防弾チョッキ3型の上からBHI(ブラックホーク)社製のH型ショルダーハーネスを装着し、腰部の弾帯を懸架している。

▲懸架された弾帯の正面には小銃用の弾倉ポーチ、左腰部にはロールアップ式のダンプポーチが装着されている。グローブは米軍など欧米のタクティカルユースで愛用者の多いMECHANIX WEAR(メカニックス・ウェア)製だ。

▲2003年のイラク派遣を契機に製作された防弾チョッキ2型にクリック・リリース分解機能を追加した防弾チョッキ2型改。当時米軍で採用されていた最新のPALSウェビング・テープ対応のIBA(インターセプター・ボディー・アーマー)に倣い、ベストの前後面に各種モジュラー・ポーチの装着に対応した日本独自規格のモジュラー・ウェビング・テープを設けている。

▲通常は両肩部分を防護するショルダー・アーマーが装着されている部分だが、今回の展示では珍しく取り外されていた。両肩部分には滑り止め加工の施されたショルダー・パッドと肩当てした銃床を固定するための小型ストッパーが設けられ、ショルダー・パッドの特徴的なデザインは、ショルダー・アーマーが内蔵式となった防弾チョッキ3型にも引き継がれている。

▲旧来の66式鉄帽の後継として、1988年に制式採用された国産の軍用バリスティック・ヘルメットである88式鉄帽。旧来の66式鉄帽が合金製だったのに対し、当時米軍で採用されたばかりの次世代軍用バリスティック・ヘルメットの先駆けであるPASGT(地上部隊個人防護システム)ヘルメットに倣い、88式鉄帽も防弾繊維を合成樹脂で積層加工した軽量な複合素材で成形されている。PASGTヘルメットに比べ、後頭部や側頭部が浅めなのが外観上の特徴だ。2013年ころからは帽体の形状はそのままに成形素材の軽量化を図り、2点式であった顎紐を安定性の高い4点式に変更するなどした改良型の88式鉄帽2型が配備されている。なお、88式鉄帽の防弾性能については一切公表されていないが、諸外国の軍用ヘルメットと同等(大抵の拳銃弾への抗弾能力を有するNIJ規格レベルIIIA)と推測される。

▲インナーデザインは米軍が採用していたPASGTヘルメットに近く、ハンモック式のヘッドサスペンションを採用している。2点式顎紐の着脱には金属板を用いた日本独自の固定方式が用いられているが、レプリカでは省略されることが多い。

▲偵察用や連絡用に用いられる排気量250ccのオフロード用オートバイであるカワサキKLX250も展示されていた。

▲基本的な仕様は市販車と同じだが、ステップ前方の堅牢なガードや車体後部の無線機搭載用ラックなど細部が異なる。
第30普通科連隊の皆様、当日は終始ご丁寧に対応して頂き、ありがとうございました。
皆様のご健勝とご活躍をお祈りしております。
それでは!
イベントの詳細は、自衛隊新潟地方協力本部のウェブサイトをご覧ください。
日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)
架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT
JP-SWAT on YouTube
 |
2016年07月23日
最近の陸上自衛隊普通科隊員装備 #01

先日、一般公開された護衛艦「せとぎり」ネタ第3弾でございます。
今回はもはや海自は関係なく、埠頭において展示を行っていた陸上自衛隊にフォーカスをあてたいと思います。
当日は陸上自衛隊新発田駐屯地に所在する第12旅団隷下の第30普通科連隊から、高機動車、軽装甲機動車、82式指揮通信車、偵察オートバイが出張展示を行いました。
また、防弾チョッキや88式鉄帽などの個人装備の試着体験ブースなども開設。
装甲車の前には、完全装備の普通科隊員の皆様が並んでおり、見学者からの質問や記念撮影などに快く応じてくれました。
中でも気合の入った装備を身にまとう隊員さんに注目し、個人装備を紹介したいと思います。

▲戦闘装着セットの普及が本格化した20年ほど前に比べ、普通科隊員の個人装備の様相は大きな進化を遂げており、海外派遣や米軍との共同訓練などを通じ、先進各国の歩兵装備に比肩する実戦的なブラッシュアップが見て取れる。

▲旧来の66式鉄帽の後継として、1988年に制式採用された国産の軍用バリスティック・ヘルメットである88式鉄帽。旧来の66式鉄帽が合金製だったのに対し、当時米軍で採用されたばかりの次世代軍用バリスティック・ヘルメットの先駆けであるPASGT(地上部隊個人防護システム)ヘルメットに倣い、88式鉄帽も防弾繊維を合成樹脂で積層加工した軽量な複合素材で成形されている。PASGTヘルメットに比べ、後頭部や側頭部が浅めなのが外観上の特徴だ。2013年ころからは帽体の形状はそのままに成形素材の軽量化を図り、2点式であった顎紐を安定性の高い4点式に変更するなどした改良型の88式鉄帽2型が配備されている。特徴的な4点式顎紐から本品も一見すると改良型の2型に見間違うが、支給の開始されたばかりの2型の更新速度は遅く、当分の間は一線部隊でも従来型が主力となる本品も従来型の2点式顎紐を隊員が個人的に購入した市販品の4点式顎紐へ換装し、快適性を高めたカスタム品だ。

▲88式鉄帽に並び、戦闘装着セットの中核であった戦闘防弾チョッキの第三世代である最新の防弾チョッキ3型を着用し、その上から私物のチェストリグを装着している。2014年ころから配備の開始された防弾チョッキ3型は、陸上自衛隊のイラク派遣を契機に製作された防弾チョッキ2型の次世代型であり、モジュラー・ウェビング・システムの改良や軽量化など快適性の追求をはじめ、先進各国で採用されている軍用ボディーアーマーに倣った実戦的な改良が施されている。

▲両肩部分には滑り止め加工の施された特徴的なショルダーパッドが装備され、銃床を肩付けした際に銃床を固定する。小型のストッパーも設けられている。国章などを貼付するために標準で設けられたベルクロスペースにも注目したい。

▲戦闘服は支給の迷彩服3型ではなく、米軍などで普及しているタイプの私物の新迷彩柄コンバットシャツであり、通常の戦闘服に比べて通気性や発汗性に優れているため、ボディーアーマー着用時の快適性が高いのが特徴だ

▲防弾チョッキ3型の背面には、米軍などで採用されている背負い式のハイドレーション・システムを携行している。従来の水筒に比べ、給水チューブを利用することで戦闘状況などの高リスク環境下でも迅速な水分補給が可能だ

▲グローブは米軍など欧米のタクティカルユースで愛用者の多いMECHANIX WEAR(メカニックス・ウェア)製だ。元々はカーレース向けの作業用グローブであったが、保護性能を維持しながら繊細な作業を可能とする素肌に近いフィット感やフィーリングの高さを有しているため、軍事や産業など分野を問わず様々な業種に普及している

▲チェストリグの前面に装着されている弾倉ポーチは、PPM(パトリオット・パフォーマンス・マテリアル)社製だ。モジュラーポーチの装着に対応した防弾チョッキ2型や3型が全面普及したにも関わらず、なぜチェストリグを愛用する隊員が多いのかは、実のところ事務的な理由が強いようだ。個人貸与された他の個人装具と異なり、防弾チョッキは火器類と同じ部隊での定期的な員数点検が義務づけられている一括管理品扱いであるため、訓練終了後は防弾チョッキを保管庫に格納しなければならない。このため、個人がいつでもポーチ類を自由にセットアップでき、訓練時に防弾チョッキの上から簡単に重ね着できるチェストリグの愛用者が多いのだという。

▲携行している弾倉は、89式小銃の標準弾倉ではなく、米軍に支給されているものと同じSTANAG弾倉である。89式小銃は米軍との相互運用性を考慮してNATO標準のSTANAG弾倉の運用が可能な設計だが、米軍支給のSTANAG弾倉がアルミ製のため軽量で錆びにくいのに対して、89式小銃の標準弾倉はスチール製で強度は高いが重量もあり錆びやすいため、近年は米軍との共同訓練などで入手したSTANAG弾倉を代替品に利用する隊員が多いようだ。

▲ライトポーチには、タンカラーのLEDライトであるSUREFIRE社製G2Lが収納されている。

▲米海兵隊に支給されているモデルと同じタンカラーのCSM社製ダンプポーチ。

▲アイウェアは米軍でも愛用者の多いRevision Military(レビジョン・ミリタリー)社製。

▲フットウェアも支給品の半長靴ではなく、より機能性が高く履き心地のよい私物のジャンブルブーツだ。

▲自衛隊初の国産装輪装甲車である82式指揮通信車(CCV)。普通科連隊では本部管理中隊に配備されている。

▲歩兵機動車の一種であり、普通科部隊の足となる軽装甲機動車(LAV:Light Armoured Vehicle)。上部ハッチのターレットに設けられた防楯付き銃架には、分隊支援火器である5.56mm機関銃MINIMIを装着運用することが可能だ。また、上部ハッチからは普通科中隊の対戦車小隊等に配備されている01式軽対戦車誘導弾(LMAT)の射撃運用も行える。
第30普通科連隊の皆様、当日は終始ご丁寧に対応して頂き、ありがとうございました。
皆様のご健勝とご活躍をお祈りしております。
それでは!
イベントの詳細は、自衛隊新潟地方協力本部のウェブサイトをご覧ください。
日本警察特殊部隊愛好会(JP-SWAT)
架空私設特殊部隊 Team JP-SWAT
JP-SWAT on YouTube
 |